時事問題解説
民主党の経済政策の見方
2009年8月30日は、日本の政治史にとって特筆すべき一日になりました。皆さんご存知のように、衆議院総選挙で民主党が大勝し、自民党が戦後の長い政権の座から滑り落ちた日です。すなわち、政権交代です。
今回の政権交代劇は、政治権力が単に自民党から民主党に移行しただけではありません。多くの国民が民主党に投票したのは、自民党が担ってきた経済政策の大きな転換を期待したからです。鳩山新政権の掲げるスローガンである「友愛政治」や「平成維新」の実現であり、「官」から「民」へ、「コンクリート」から「人」への政策転換に対する期待です。その政策転換の具体的な内容は、民主党の政権政策マニフェストに書かれています。
そこで、マニフェストに書かれている政策各論について、経済学の見方からすると問題のある項目を3つ取り上げてコメントしてみることにしましょう。
1.高速道路の原則無料化
高速道路は社会資本であって、公共財とは違います。たとえば国防、外交、警察などの公共サービスは「排除不可能」や「共同消費可能」の特徴を備え、不特定多数の人々、すなわち、国民全般に便益を及ぼす性質を持っています。したがって、管理・運営などに関わるコストを料金徴収でカバーすることはできないので、国民の税金で負担せざるを得ません。ところが、高速道路を利用するドライバーには、出入り口で料金を徴収することができます。
高速道路を無料にすると、諸々のコストは税金でカバーせざるを得ません。それでは「受益者負担の原則」に抵触します。言い換えると、高速道路の利用者がコストを負担すべきで、未利用者にまで要求すべきではないでしょう。これが高速道路無料化に関する第1の問題点です。
第2に、高速道路には時間を節約できるメリットがあります。高速道路を利用すると、通行料金を支払うことによって目的地に早く到着でき時間の節約になります。したがって、時間価値の高い人にとっては、一般道路よりも高速道路を利用するほうが安くなります。すなわち、高速道路の利用料金<一般道路の利用料金(=時間コスト)ならば、高速道路の利用を選択するでしょう。
第3に、高速道路を無料にすると渋滞を引き起こし兼ねません。事実、土日の高速料金を一律千円にした結果、渋滞発生回数は94%増加しました(「財団法人運輸調査局」の調べ)。まさに低速道路になってしまい、時間コストを節約するという本来の機能を失う事態になってしまいました。したがって、高速サービスを維持できるような料金体系にすべきでしょう。たとえば、オフ・ピークや夜間の料金を引き下げて高速道路の利用を分散させるほうが、高速道路のスムーズな走行を維持するためには効果的でしょう。
第4に、米国やドイツの高速道路は原則無料であるという議論がしばしば引き合いに出されます。しかし、各国の料金と比較検討する場合には、公共交通機関やその他の移動手段の発達具合、あるいは、日常生活におけるクルマの必要性などを考慮して、総合的に判断すべきです。高速道路の料金そのものを単純に比較するのは無意味です。
最後に、民主党のマニフェストには、高速道路を無料化する目的として、「地域経済の活性化を図る」と謳われています。果たして、地方の高速道路を無料にしても、地方経済の活性化に結びつくでしょうか。大いに疑問です。むしろ、地方の活性化を図る目的ならば、他の政策で手当てするほうが効果的でしょう。また、物流コストが下がり、商品価格が安くなるメリットもあると主張されています。そのような効果があるなら、物流輸送車に対して高速道路料金の割引制度を導入するのも一つの方法でしょう。
2.最低賃金の引き上げ
民主党のマニフェストには、最低賃金を引き上げる政策目的として、「まじめに働いている人が生計を立てられるようにし、ワーキングプアからの脱却を支援する」と書かれています。果たして、最低賃金の引き上げは政策目的に適うでしょうか。
経済の基本は「分業」と「交換(取引)」です。労働サービスを供給する労働者と、それを需要する企業の間での取引もその一つです。そして、労働サービスを供給する見返りに賃金が支払われます。図1には、労働サービスの供給と需要の様子が描かれています。まず、企業の求人数と賃金の関係は右下がりのD曲線で描かれ、賃金の下落(上昇)は求人
図1 最低賃金制度

数を増加(減少)させます。労働者の求職者数と賃金の関係は右上がりのS曲線で描かれ、賃金の下落(上昇)は求職者数を減少(増加)させます。
さて、現行の労働市場での賃金(W*)は低すぎるため(図1のE*点)、最低賃金を引き上げようとするのでしょう。そこで、最低賃金がW₀(>W*)に決められたとしましょう。賃金が上昇したので、企業は求人数をN*からN1へと減らすでしょう。一方、働らきたい人はN*からN2へと増えます。その結果、有効求人倍率は下がり、失業率は上昇します。
問題はN*人の一部が失業するだけではありません。最低賃金W₀の下では、求職者数はN2人いますが、そのうちN1人しか就職できません。運よく就職できる労働者の中には、賃金がW₀以上なら働いてもいいと思う(N2-N*)人が、新たに労働市場に参入してきます。その人たちによって、現行の賃金W*でも働きたいと願っている人を失業させてしまうことも起こり得ます。ワーキングプアからの脱却どころか、現在就業している労働者を失業という一層惨めな状態に落とし込んでしまい兼ねません。
最低賃金制度が導入されると、それが遵守されているか否かを監視しなければなりません。このような監視コストも掛かるでしょう。さらに、労働市場に潜在的に働きたい人が大勢いる不均衡な状態が続くと、ブラック・マーケットが横行し、斡旋業者の搾取やピンハネなどの不法行為がまかり通るリスクが高まります。それに対処するために、さらに監視を強化する必要が出てくるでしょう。
長期的な影響としては、最低賃金の引き上げによる労働コストの増加を避けるために、企業は生産拠点を賃金の低い海外へシフトさせるでしょう。すると、国内の求人数はさらに減少します。すなわち、D曲線が左方向にシフトすることになり、失業率もさらに悪化することでしょう。
それでは、ワーキングプアから脱却するためには、どうすればいいでしょうか。いうまでもなく、景気が良くなることです。景気が良くなれば、D曲線は右方向にシフトし、賃金水準もW*よりも高くなるでしょう。したがって、景気対策は必要不可欠です。しかし、景気対策は即効薬にはなりません。むしろ、ワーキングプアからの脱却は福祉政策の分野でもあります。
低い賃金で働いている人の生活を保障するのが福祉政策です。そこで、一つの方法として「負の所得税」の導入が考えられます。それを図2で説明しましょう。図2の横軸は税引き前の所得(Y)で、縦軸は税引き後の所得(Yd)です。税金がなければY=Ydなので、45°線で示されます。現行の租税制度では、基礎控除などの最低所得(Y₀)以上の所得に対して課税されます。したがって、課税所得以下(Y<Y₀)なら納税する必要がないので、Y=Ydになります。そして、課税所得がY₀以上になると納税義務が生じます。実際の税率は課税所得が高くなると税率が上昇する累進税率です。しかし、ここでは簡単化のために、税率は一定(100×t%)の比例税率を想定しましょう。すると、税引き後の所得はYd=(1-t)Yとなります。図2では、税引き後の所得はE点までが45°線で、それを超えると太線の所得で示されます。
図2 負の所得税
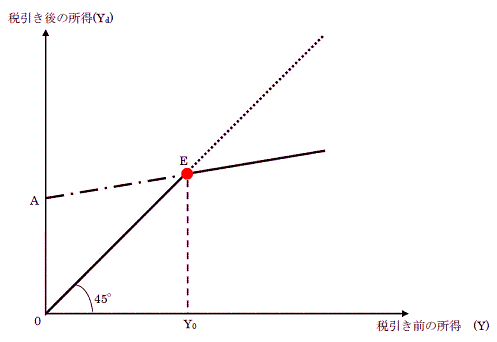
それでは、「負の所得税」が導入されると、どうなるでしょうか。「負の所得税」とは、所得の低い人に補助金を支給することです。図2に即して言えば、Y₀以下の所得に対して補助金を与えることになります。ただし、全員一律の同じ支給額ではなく、所得の低い人ほど支給額が多くなります。いま、Y=0の人に支給される額(たとえば、生活保護費に相当)をA円とすれば、Yが増えるに従ってYdはそれ以上の額になります。図2では、税引き後の所得はE点までが45°線よりも上の破線で示されます。そして、E点を超えると、現行の状態と同じになります。この結果、まじめに働いている人は最低額A円以上の所得が確保できるので、民主党の主張する「人にやさしい」政策にもなります。また、働いている人の手取り収入が生活保護費を下回るような奇妙な現象も避けられ、結果として事実上最低賃金を確保することにもなります。
3.製造現場への派遣原則禁止
結論から先に言えば、派遣労働を禁止しても、派遣労働者から請負会社やその他の非正規労働者にシフトするだけで、政策目的である労働者への待遇改善には繋がらないでしょう。あるいは、最低賃金制度と同じで、企業は海外生産へシフトし、雇用機会が減ってしまい兼ねません。
わが国の非正規労働者の割合は年々増え続け、現在では就業者の34.1%(2008年)も占めています。それでは、なぜ非正規労働者の割合が増えてきたのでしょうか。この問題を明らかにしない限り、単に派遣労働の禁止だけを決めても問題の根本的な解決にはならないでしょう。
非正規労働者が増えた背景には、日本経済を取り巻くマクロ環境の大きな変化が関わっています。その主な変化とは、①高度経済成長から低成長時代への変化と、②グローバル化による非競争社会から競争社会への変化です。そこで、マクロ環境の変化前と後における大企業のプライシング(価格設定)について説明しましょう。
図3と図4の横軸は製造業の生産量を、縦軸は生産物価格を表わしています。そして、生産物に対する需要がD曲線です。まず、図3には高度成長時代における非競争社会の状況が描かれています。非競争社会の大企業は価格支配力を持っているので、単位当たりの製造原価に利潤マージン(図の斜線部)を加えて生産物価格を決めます。このようにして、生産物価格がP1円に設定されると、生産物の需要量はX1単位になります。そこで、原材料費や人件費が上昇すれば製造原価は増えます。ところが、大企業はこのコスト増加分を生産物価格に転嫁します。すると、コスト増加分に利潤マージンを加えた生産物価格はP2円に上昇します。もしD曲線が変化しなければ、生産物価格が上昇したので需要量は減少するでしょう。ところが、高度成長によって国民の所得は増え生産物への需要が増えると、D曲線は右にシフトします。そして、新しいD'曲線の下では、たとえ生産物価格が上昇しても生産物需要が増え、生産量はX2単位まで増大していくのです。さらに、製造業の生産量が増えると「規模の経済性」が働き、製造原価を下げる効果も現われてくるでしょう。このような状況にあったからこそ、大企業は正規労働者として雇用し続けることができたのです。
図3 高度成長と非競争社会
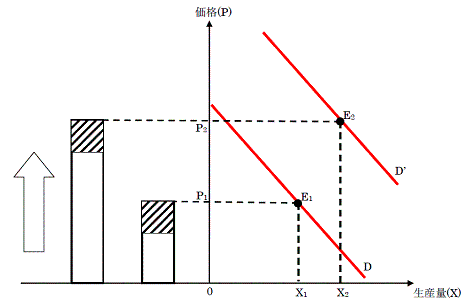
しかし、グローバル化が進展すると、日本経済の環境も競争社会へと変貌していきます。さらに、高度成長も終わり、低成長時代に推移してきました。競争社会では、大企業の生産物価格を支配する力は弱まり、価格はマーケット(市場)で決まるようになります。その状況が図4で描かれていますが、生産物価格は需要と供給が一致するP1円で販売せざるを得なくなるのです。そして、一定の利潤マージンを確保しようとすれば、製造原価をそれ以下に抑える必要があります。さらに競争が激しくなって、中国やアジア諸国の企業が市場に参入すると供給が増えます。すなわち、S曲線からS'曲線にシフトします。一方、低成長時代のため、需要は余り増えないでしょう。すると、生産物価格はP1円からP2円へと下落するでしょう。このような状況下で、大企業が一定のマージンを確保するためには、さらなる製造原価の引き下げが求められるのです。その結果、大企業はリストラ(再構築)の必要性に迫られ、その一環として正規雇用者の削減や非正規雇用者の割合を増加させることで対処せざるを得なくなったのです。
図4 低成長と競争社会
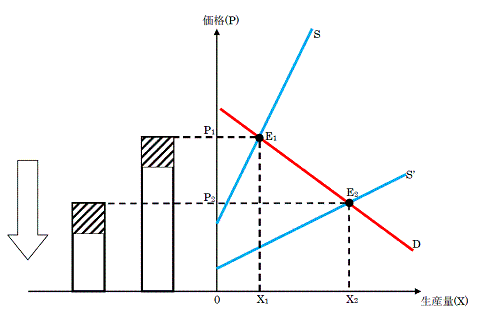
要約すれば、高度成長・非競争社会では「コストありき」(図3の上向き矢印)だったのが、低成長・競争社会では「価格ありき」(図4の下向き矢印)に変化したのです。グローバル化の中で、競争に勝ち残るために労働者の非正規化は避けて通れない対応なのです。
それでは、このようなグローバル化の中で、日本経済はどのような方法で対処すべきなのでしょうか。高度成長期後の1974~90年まで、年平均の労働生産性は製造業で約4.4%、サービス産業で約1.0%でした。この間、日本の産業構造は経済のソフト化・サービス化へと転換してきました。現在では、就業者数の比率は第二次産業で約27%、第三次産業で約68%を占めています。そこで、これらの値を用いて日本全体の労働生産性を単純に加重平均して計算すると、僅か1.9%(=0.27×4.4+0.68×1.0)にしかなりません。したがって、今後、日本経済の生産性を引き上げるためには、労働集約的なサービス業の生産性を高めることが肝要です。そのため、ポスト工業社会における雇用政策は、労働集約的なサービス業の生産性を引き上げるためにも、知識労働者の育成が非常に重要であり、それが日本社会の新たな目指すべき雇用政策の道でしょう。
(同志社大学経済学部 教授 西村理)